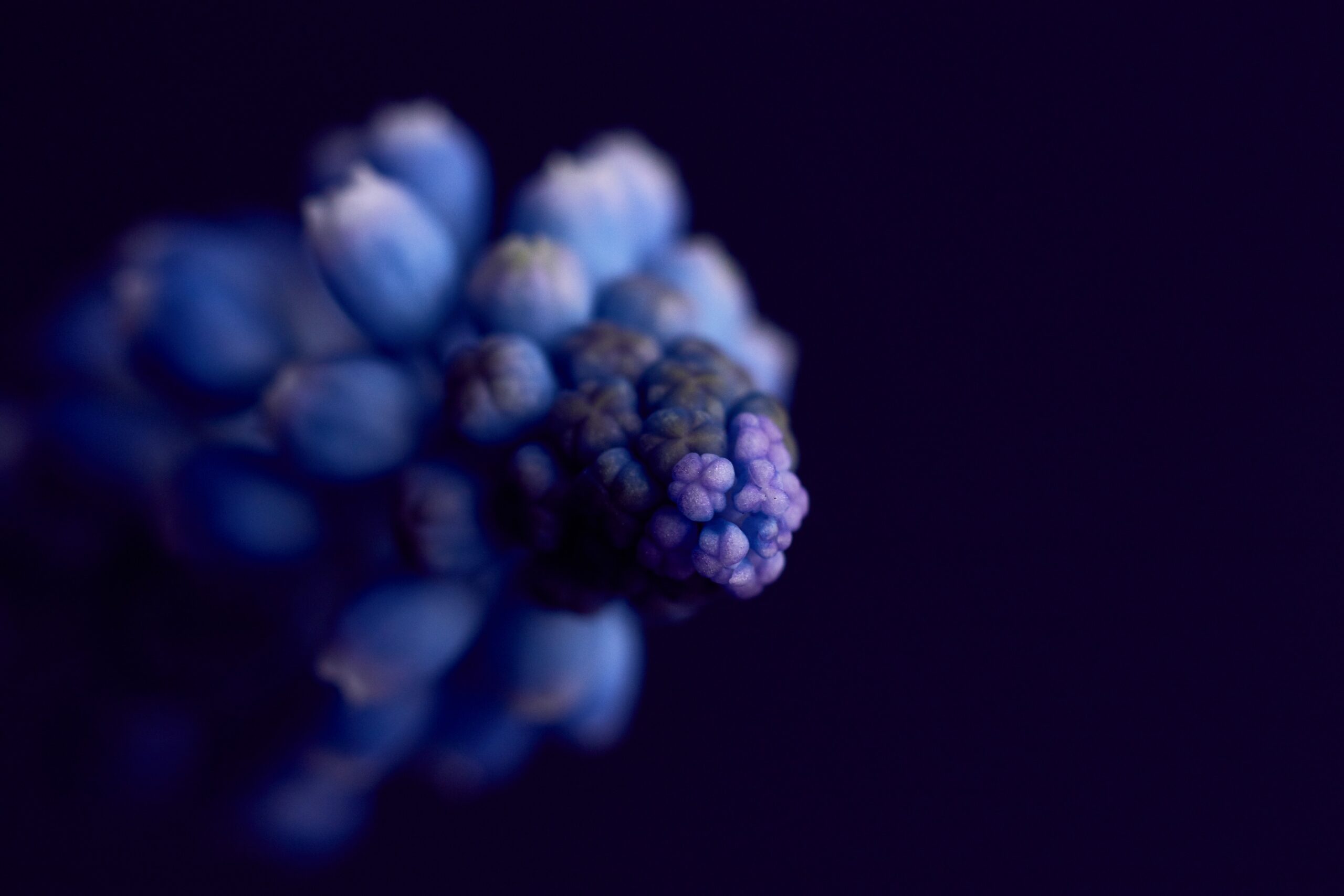解離(dissociation)は、私たちの意識、記憶、自己同一性、知覚、身体感覚、行動などが通常は統合されている状態から、一時的または慢性的に切り離される体験を指します。極度のストレスやトラウマに対する防衛反応として生じることがありますが、そのメカニズムや現れ方は非常に複雑で、専門家の間でも様々な見解が存在します。
本記事では、解離を理解するための主要な理論的アプローチを概観し、それぞれの視点が解離現象をどのように捉え、説明しようとしているのかを探ります。
- 心的外傷関連構造的解離理論 (Theory of Trauma-Related Structural Dissociation of the Personality)
- 離散的行動状態理論 (Discrete Behavioral States Theory: DBST)
- 解離の知覚理論 (Perceptual Theory of Dissociation: PTD)
- 文脈的解離理論 (Contextual Dissociation Theory: CTT)
- 4次元(4-D)モデル (Four-Dimensional Model)
- 解離と未形成の経験 (Dissociation and Unformulated Experience) – 精神分析的モデル
- まとめ
- 参考文献
心的外傷関連構造的解離理論 (Theory of Trauma-Related Structural Dissociation of the Personality)
提唱者: Onno van der Hart, Kathy Steele, Ellert Nijenhuis ら
この理論は、ピエール・ジャネやチャールズ・マイヤーズといった歴史的な概念に基づき、現代のトラウマ研究や神経生物学、アタッチメント理論などを統合しようとする試みです (Van der Hart & Dorahy, Chapter 1; Van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2006)。
中核概念:
- 人格の定義: 人格を個人の特徴的な精神的・行動的活動を決定する生物心理社会的なシステムとして捉えます (Allport, 1961; Nijenhuis, 2015)。
- 統合能力の低下: 深刻なトラウマ体験は、人格の統合能力を低下させ、人格システムが部分に分裂(構造的解離)すると考えます。これは主に統合能力の欠如による「解離性の混乱と再組織化」であり、二次的に心理的防衛として機能します (Van der Hart et al., 2006)。
- ANPとEP: 人格は、日常生活機能(アタッチメント、探索、遊び、ケアなど)を担う「見かけ上正常な人格部分(Apparently Normal Part: ANP)」と、トラウマ体験に固着し、侵入症状(フラッシュバック、強い情動など)として現れる「情動的人格部分(Emotional Part: EP)」に分裂します。ANPはトラウマ記憶を恐怖症的に回避し、EPはトラウマ時の感覚運動的・情動的体験を再演します (Myers, 1940; Van der Hart et al., 2006)。
- 解離の段階: 単純なPTSD(ANP×1、EP×1)を「一次構造的解離」、複数のEPが存在する複雑性PTSDや特定不能の解離性障害(OSDD)、境界性パーソナリティ障害(BPD)の一部を「二次構造的解離」、複数のANPと複数のEPが存在する解離性同一性障害(DID)を「三次構造的解離」として説明します (Nijenhuis, 2015; Van der Hart et al., 2006)。
- 行動システム: 人格部分の分裂は、生得的な行動システム(アタッチメント、防衛(闘争・逃走・凍りつき・気絶)、探索、遊び、性、ケアなど)の間の非統合に基づくと考えられます。特に、虐待的な養育者へのアタッチメントと防衛という相反する行動システムの葛藤が、解離の基本的な断層線となります (Liotti, 1999a; Panksepp, 1998; Van der Hart et al., 2006)。
- 統合(Synthesis)と現実化(Realization): 精神的健康は、経験を統合(様々な要素を結びつけ、時間軸で一貫性を持たせる)し、現実化(自己のものとして所有し、現在に適用する)する能力によって特徴づけられます。トラウマはこれらの能力を阻害し、「非現実化(non-realization)」の状態(解離の中核)を引き起こします (Janet, 1935; Van der Hart et al., 2006)。
臨床的意義: 治療は、ANPの安定化、ANPとEP間のコミュニケーションと協調性の促進、トラウマ記憶の段階的処理、そして最終的な人格の統合を目指す段階的アプローチ(安定化、トラウマ処理、統合とリハビリテーション)が推奨されます (ISSTD, 2011; Steele, Boon, & Van der Hart, 2017)。
離散的行動状態理論 (Discrete Behavioral States Theory: DBST)
提唱者: Frank W. Putnam, Richard J. Loewenstein
DBSTは、人間の意識と行動を、特定の時間枠内で繰り返される心、身体、脳の変数のパターンである「離散的行動状態(Discrete Behavioral States: DBS)」または「存在状態(States of Being: SoB)」として捉える、理論横断的・トランスレーショナルな理論です (Putnam, 2016)。
中核概念:
- 状態(State): 各状態は、知覚、認知、記憶、情動、動機づけ、価値観、精神生理、対人相互作用に独自の影響を与えます。睡眠-覚醒サイクル、気分状態、注意状態などが含まれます (Putnam, 2016)。
- 状態依存性: 学習や記憶(State-dependent learning and memory: SDLM)は特定の状態に依存しており、異なる状態ではアクセスが困難になることがあります。これは解離性健忘(DA)の重要なメカニズムと考えられます。
- 乳幼児期の状態: 健康な新生児は、規則的睡眠、不規則睡眠、覚醒静止、覚醒活動、啼泣といった基本的な行動状態を持ち、これらが周期的に切り替わります。これらの状態とその移行は、後の全ての人間行動状態の核を形成します (Prechtl & O’Brian, 1982; Wolff, 1987)。
- アタッチメントとアチューンメント: 養育者とのアチューンメント(同調)は、乳幼児の状態調節と自己調節能力の発達に不可欠です。不適切なアタッチメントは、状態間の統合不全を引き起こし、後の解離性障害の基盤となる可能性があります。
- 精神病理: PTSDやDIDなどの多くの精神疾患は、「状態変化障害(state-change disorders)」として概念化できます。症状の変動や再発は、病的な状態への移行や状態間の調節不全として理解されます。DIDは、異なる自己状態(self-states)が未統合のまま存在する、発達上の状態変化障害の典型とされます (Putnam, 1997)。
- 解離の概念化: 解離は、生命を脅かす危険に対する精神生物学的反応の重要な部分です。急性解離反応では、生理機能、知覚、自己感覚などが変化した意識状態が生じ、トラウマ記憶はこの状態で符号化されます。SDLMにより、後でこれらの体験へのアクセスが制限され、健忘が生じます。
臨床的意義: DBSTは、様々な精神疾患における症状の変動性や治療プロセスを理解するための枠組みを提供します。治療においては、状態間の認識、調節、統合を促進することが重要となります。DIDの治療では、異なる自己状態間のコミュニケーションと協調、そして機能的な統合を目指します。
解離の知覚理論 (Perceptual Theory of Dissociation: PTD)
提唱者: Donald B. Beere
PTDは、現象学(特にメルロ=ポンティ)と自己システム理論(サリヴァン)を基盤とし、解離を知覚の変化として説明する理論です (Beere, 2009a; Merleau-Ponty, 1962; Sullivan, 1956)。
中核概念:
- 知覚の構造: 知覚は常に「図(figure)」と「地(ground)」、そしてそれらを取り巻く「背景(background)」から構成されます。背景には、自己(I)、心(Mind)、身体(Body)、世界(World)、時間(Time)という5つの基本的な構成要素が含まれます。
- 解離のメカニズム: 脅威的な状況下で、注意が特定の対象(決定的な重要性を持つ知覚対象 “percept of determining significance”)に極度に集中(ハイパーフォーカス)すると、背景の構成要素(自己、心、身体、世界、時間)への知覚が遮断または歪められ、解離体験が生じます。これは自発的かつ非意図的なプロセスです (Beere, 1995a)。どの背景要素が影響を受けるかは、脅威の焦点とは逆に関連します(例:身体への脅威→心や世界の解離)。
- 解離の複雑性: 解離現象は心理的複雑性の連続体上にあり、単純な時間感覚の変化から、複雑な解離性同一性の形成まで様々です。より複雑な解離は、より深刻で頻繁なトラウマを必要とします。
- 肯定的状況での解離: 解離はトラウマだけでなく、スポーツ、性的経験、宗教的体験、自然との一体感など、個人的に「決定的な重要性」を持つ肯定的・非トラウマ的な状況でもハイパーフォーカスによって生じうることが示唆されています (Beere, 1995a; Pica & Beere, 1995)。解離は本質的に防衛や対処メカニズムではなく、ハイパーフォーカスの副産物である可能性があります。
- 自己システム (Self System): サリヴァンの概念を拡張し、自己システムを意識の構造化メカニズムとして捉えます。自己システムは経験の境界を定め、「私(me)」と「私でないもの(not-me)」を区別します。耐え難い「not-me」体験(トラウマなど)は自己システムから排除され、健忘が生じたり、離人感・現実感消失として体験されたりします。DIDは、単一の意識内に複数の自己システム(それぞれが独自のI-Mind-Body-World-Time構造を持つ)が存在する状態として理解されます (Beere, 2009b; Sullivan, 1956)。
- 現在化 (Presentification): 解離状態にあるクライエントが失われた背景要素とのつながりを再確立し、現在に「入る」ことを助けるための介入技法です。身体的動作(バランスをとる、壁に触れるなど)や知覚的弁別課題(セラピストの外見に関する質問など)を用いて、身体、世界、時間、自己といった背景要素への気づきを促します (Beere, 2009a; Van der Hart, Nijenhuis & Steele, 2006)。
臨床的意義: PTDは、解離症状を知覚の変化として理解し、具体的な介入法(Presentification)を提供します。治療は、クライエントが現在に安全につながり、過去のトラウマが過去のものであると認識できるよう支援することに焦点を当てます。
文脈的解離理論 (Contextual Dissociation Theory: CTT)
提唱者: Steven N. Gold
CTTは、解離を適応的な側面も持つ人間の基本的な機能と捉え、特に複雑な解離(幼少期の長期的な虐待に関連するもの)を、トラウマ体験だけでなく「発達的剥奪(developmental deprivation)」の結果としても理解する理論です (Gold, 2000, 2020)。
中核概念:
- 解離の本質: 解離は文字通りの「切断(disconnection)」であり、個人的領域(感覚、知覚、情動、認知)、対人関係領域(疎外感、親密さの欠如)、環境領域(周囲への気づきの低下)のいずれか、または複数における体験的気づきからの切断・距離化として現れます。
- 発達的剥奪: 安全なアタッチメントや適切な養育環境の欠如は、注意の持続・調整能力、情動認識・調節能力、自己感覚の統合といった心理的発達を阻害します。この発達上の欠損が、複雑性解離の基盤となると考えます。これはトラウマによる機能不全(獲得した能力の阻害)とは区別される「スキル欠損(skills deficit)」です。
- 単純解離 vs 複雑解離: 成人期の単回性トラウマによる解離(単純解離、例:PTSD)は主にトラウマ症状(侵入、回避、過覚醒)による注意・気づきの妨害に起因します。一方、長期的な児童虐待(PCA)サバイバーに見られる解離(複雑解離、例:C-PTSD、DID)は、トラウマ反応に加えて、発達的剥奪による持続的な解離的状態(例:同一性の混乱・断片化、広範な健忘)を特徴とします。
- 接続(Connection): 心理的発達は、他者、自己の主観的経験、周囲の世界との「接続」能力が増大していくプロセスです。対人関係における接続(特に初期の養育者との安定した相互作用)が、脳の発達と内的統合を促進します。発達的剥奪は、この接続能力の基盤を弱め、さらなる発達を阻害します (Siegel, 1999, 2020)。
- 発達的解離現象: CTTは、従来の解離症状には含まれないが、発達的剥奪に起因する解離的性質を持つ現象(例:両側性統合の欠如、視覚的協応不全による平面的な世界認識、情動的対象恒常性の欠如、アレキシサイミア、他者との繋がり感の欠如、慢性的な離人感・体外離脱感)にも注目します。
臨床的意義: CTTは、複雑性トラウマサバイバーの治療において、トラウマ処理だけでなく、発達的欠損(スキル欠損)の修復(発見のプロセス)が不可欠であると強調します。治療関係におけるセラピストの一貫した注意と応答性が、クライエントの接続能力の発達を促す鍵となります。
4次元(4-D)モデル (Four-Dimensional Model)
提唱者: Paul Frewen, Ruth A. Lanius, Serena Wong
4-Dモデルは、解離体験を時間(Time)、思考(Thought)、身体(Body)、情動(Emotion)という4つの意識次元における変化として捉える、現象学に基づいた枠組みです (Frewen & Lanius, 2015)。
中核概念:
- 正常覚醒意識 (NWC) vs 変性意識状態 (ASC): 各次元における通常の体験様式(NWC)を定義し、解離体験(特にトラウマ関連変性意識状態: TRASC)をNWCからの逸脱として記述します。
- 時間: NWCでは過去と現在を区別できる。TRASCでは過去と現在の混同(例:フラッシュバック)が生じる。
- 思考: NWCでは思考は一人称(1PP)で生じる。TRASCでは思考が一人称以外(例:二人称/三人称、声の聴取)で体験される。
- 身体: NWCでは身体化された(embodied)意識を持つ。TRASCでは離人感、体外離脱体験など非身体化(disembodied)が生じる。
- 情動: NWCでは多様な情動を感じることができる。TRASCでは著しい情動麻痺が生じる。
- 症状の分類: PTSD症状を、NWCの定義を侵害しない「NWC苦痛症状」(例:侵入的記憶、悪夢、回避)と、NWCの定義を侵害する「TRASC症状」(例:フラッシュバック、声の聴取、離人感、情動麻痺)に分類します。
- 経験の断片化と構造的解離: 4-Dモデルは、意識状態の変化(ASC)だけでなく、心理機能の断片化(compartmentalization)や人格の構造的解離(structural dissociation)のプロセスも説明しようとします。(非)自己関連処理モデル((N-)SRP model)を用いて、ストレス下での自己関連処理(SRP)から非自己関連処理(N-SRP)への移行(断片化)、さらには他者関連処理(ORP)への移行(構造的解離)を説明します。
- PTSDの解離性サブタイプ: DSM-5のPTSD解離性サブタイプ(D-PTSD)の概念と一致し、TRASC症状が顕著な場合に診断されると考えます。
臨床的意義: 4-Dモデルは、トラウマ関連障害のアセスメントにおいて、NWC苦痛症状とTRASC症状を区別することの重要性を強調します。TRASC症状の治療には、これらの変性意識状態に直接介入するアプローチが必要になる可能性を示唆しています。
解離と未形成の経験 (Dissociation and Unformulated Experience) – 精神分析的モデル
提唱者: Donnel B. Stern
このモデルは、ハリー・スタック・サリヴァンの対人関係論的精神分析と解釈学(特にガダマー)に影響を受け、解離を抑圧とは異なる主要な防衛機制であり、経験が形成されるプロセスそのものに関わる現象として捉えます (Stern, 1997, 2010; Sullivan, 1953)。
中核概念:
- 抑圧モデルとの対比: 古典的な抑圧モデルでは、意識は自然な状態であり、不快な内容(欲動由来)が無意識に押し込められると考えます。意識の内容は既に形成されており、防衛はそれを認識することへの拒絶です。
- 未形成の経験 (Unformulated Experience): 解離モデルでは、経験は最初から明確に形成されているのではなく、「未形成」の状態から能動的な努力(好奇心)によって言語的・反省的意味または非言語的・手続き的意味へと「形成」されると考えます。意識は受動的な記録ではなく、能動的な創造です。
- 解離の定義: 解離は、未形成の経験の可能性を、言語的・非言語的な象徴的形態へと形成(構定)することへの無意識的な不本意さ・不能性です。これは、既に存在する内容を否認するのではなく、経験が形を持つこと自体を防ぐプロセスです。
- 好奇心 (Curiosity): 好奇心は、未形成の経験に対して開かれ、それを形成しようとする能動的な態度です。解離は好奇心の欠如・拒絶であり、慣習的で予測可能な経験への固執です。
- 対人関係領域 (Interpersonal Field): 理解や意味の形成は、対話や他者との関係性の中で起こります。対人関係領域(現実の他者および内的対象との関係)が、どのような経験が形成され、何が真実となるかを大きく決定します。解離もまた、対人関係領域に相対的な現象です。
- 能動的解離 vs 受動的解離: 防衛的な目的(耐え難いnot-me体験の回避)のために経験の形成を能動的に(無意識的に)拒絶する「強い意味での解離(能動的解離)」と、単に注意が他の場所にあるために経験の可能性が形成されないままになる「弱い意味での解離(受動的解離)」を区別します。
- 自己状態 (Self-states): 能動的解離は、特定の自己状態が耐えられない経験内容を排除し、その内容を知りうる別の自己状態から防衛的に隔離することと等価です。
- 想像力 (Imagination): 解離は想像力の自由な働きを妨げるものです。想像力は、言語的・非言語的な意味が自由に生起することを可能にする能力であり、解離はその可能性を狭めます。
臨床的意義: 治療は、クライエントが未形成の経験に対して好奇心を持ち、それを(言語的・非言語的に)形成できるようになることを目指します。治療的相互作用(enactment)の中で、解離によって制限されていた想像力や関係性の自由度(relational freedom)を取り戻すことが重要となります。
まとめ
解離は、単一のメカニズムで説明できる現象ではなく、トラウマ、発達、知覚、意識状態、対人関係、そして経験の形成プロセスといった多様な側面から理解されるべき複雑な構成概念です。
- 構造的解離理論は、トラウマによる人格構造の分裂と機能不全に焦点を当てます。
- 離散的行動状態理論は、意識と行動の状態変化という観点から解離を捉えます。
- 知覚理論は、注意のハイパーフォーカスと背景知覚の喪失というメカニズムを提示します。
- 文脈的解離理論は、トラウマだけでなく発達的剥奪の重要性を強調し、解離を接続の欠如として捉えます。
- 4-Dモデルは、時間、思考、身体、情動という次元における意識の変容として解離を現象学的に記述します。
- 精神分析的モデルは、解離を経験が形成されるプロセスにおける防衛的な失敗、好奇心の欠如として概念化します。
これらの理論は、それぞれ異なる側面を強調し、時には相互に補完し、時には異なる見解を提示します。臨床家や研究者は、これらの多様な視点を理解し、統合することで、解離という複雑な現象に対するより深く、包括的な理解を得ることができるでしょう。そして、その理解は、解離に苦しむ人々へのより効果的な支援につながるはずです。
参考文献
- Allport, G. W. (1961). Pattern and growth in personality. Holt, Reinhart & Winston.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Author.
- Beere, D. B. (1995a). Loss of “Background”: A perceptual theory of dissociation. Dissociation, 8, 166–174.
- Beere, D. B. (2009a). Dissociative Perceptual Reactions: The Perceptual Theory of Dissociation. In P. Dell & J. O’Neil (Eds.), Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond (pp. 209–222). Routledge.
- Beere, D. B. (2009b). The Self-system as “Mechanism” for the Dissociative Disorders: An Extension of the Perceptual Theory of Dissociation. In P. Dell & J. O’Neil (Eds.), Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond (pp. 277–285). Routledge.
- Frewen, P. A., & Lanius, R. A. (2015). Healing the traumatized self: Consciousness, neuroscience, treatment. W. W Norton & Company.
- Gold, S. N. (2000). Not trauma alone: Therapy for child abuse survivors in family and social context. Brunner-Routledge.
- Gold, S. N. (2020). Contextual trauma therapy: Overcoming traumatization and reaching full potential. American Psychological Association.
- International Society for the Study of Trauma and Dissociation [ISSTD]. (2011). Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, third revision. Journal of Trauma & Dissociation, 12, 115–187.
- Janet, P. (1935). Réalisation et interprétation. Annales Médico-Psychologiques, 93, 329–366.
- Liotti, G. (1999a). Disorganization of attachment as a model for understanding dissociative psychopathology. In J. Solomon & C. George (Eds.), Attachment disorganization (pp. 297–317). Guilford.
- Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. (C. Smith, Trans.). Routledge & Kegan Paul. (Original work published 1945)
- Myers, C. S. (1940). Shell shock in France 1914–1918. Cambridge University Press.
- Nijenhuis, E. R. S. (2015). The trinity of trauma: Ignorance, fragility, and control (Vol. 1 & 2). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions. Oxford University Press.
- Pica, M., & Beere, D. B. (1995). Dissociation during positive situations. Dissociation, 8, 241–246.
- Prechtl, H. F. R., & O’Brian, M. J. (1982). Behavioral states of the full-term newborn. In P. Stratton (Ed.), Psychobiology of the Human Newborn (pp. 53–74). John Wiley & Sons.
- Putnam, F. W. (1997). Dissociation in children and adolescents: A developmental perspective. Guilford.
- Putnam, F. W. (2016). The Way We Are: How States of Mind Influence Our Identities, Personality, and Potential for Change. International Psychoanalytic Books.
- Siegel, D. J. (1999). The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience. Guilford Press.
- Siegel, D. J. (2020). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are (3rd ed.). Guilford.
- Steele, K., Boon, S., & Van der Hart, O. (2017). Treating trauma-related dissociation: A practical, integrative approach. Norton.
- Stern, D. B. (1997). Unformulated experience: From dissociation to imagination in psychoanalysis. The Analytic Press.
- Stern, D. B. (2010). Partners in thought: Working with unformulated experience, dissociation, and enactment. Routledge.
- Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. Norton.
- Sullivan, H. S. (1956). The collected works of Harry Stack Sullivan (Vols. I & II). Norton.
- Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2006). The haunted self: Chronic traumatization and the theory of structural dissociation of the personality. Norton.
- Wolff, P. H. (1987). The development of behavioral states and the expression of emotions in early childhood. University of Chicago Press.
- World Health Organization. (2020). International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.). Author.