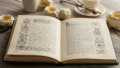はじめに
人生において、強い恐怖や生命の危機を感じる場面に遭遇したとき、私たちは時に、意図せず体が硬直し、動けなくなることがあります。これは単なるパニックや意志の弱さとして片付けられがちですが、実は「緊張性不動(Tonic Immobility: TI)」と呼ばれる、生物学的に根差した生存戦略の一部である可能性が指摘されています。
TIは、動物が捕食者からの脅威にさらされた際に見せる防御反応の一つとして古くから知られてきました。しかし近年、この反応が人間、特に性的暴行などの深刻なトラウマ体験中に起こりうること、そしてその後のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症や症状の重篤化と深く関連していることが、研究によって明らかにされつつあります。
この記事では、緊張性不動(TI)とは何か、その進化的背景、人間におけるTIの現れ方、そして特にトラウマ、とりわけ性的暴行の文脈でTIがどのようにPTSDと関連しているのかについて、最新の研究知見を交えながら掘り下げていきます。TIという現象を理解することは、トラウマサバイバーが体験中に感じた「動けなかった」という経験への自己非難を和らげ、回復への道を照らす一助となるだけでなく、私たち自身や社会がトラウマ反応への理解を深める上で不可欠です。
1. 緊張性不動(Tonic Immobility: TI)とは何か?
1.1. 動物におけるTI:進化的な防御反応
TIは、昆虫、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類に至るまで、系統発生的に広く見られる生得的な防御反応です(Gallup, 1977; Marx et al., 2008)。動物が捕食者に捕獲されたり、物理的に拘束されたりして、逃走や闘争が不可能だと判断された極限状況で引き起こされると考えられています。
これは、脅威に対する一連の防御反応カスケード(defense cascade)の最終段階に位置づけられます(Ratner, 1967; Marx et al., 2008)。脅威を察知すると、動物はまず「凍りつき(Freezing)」して動きを止め、捕食者に見つからないようにします。脅威がさらに接近すると、「逃走(Flight)」または「闘争(Fight)」によって積極的に対処しようと試みます。しかし、これらの試みが失敗し、捕獲・拘束され、逃れられないと判断されると、最終手段としてTIが発現するのです。
TIの主な特徴としては、以下が挙げられます(Gallup, 1977; Marx et al., 2008; Klemm, 1971)。
- 運動の抑制: 最も顕著な特徴で、一時的に体が動かせなくなる。
- 筋肉の硬直または弛緩: 種によって、筋肉が異常に緊張(過緊張)するか、逆に弛緩(低緊張)する。
- 無反応: 外部からの刺激(痛み刺激でさえ)に対する反応性が著しく低下する。
- 断続的な閉眼: 目を閉じている時間が長くなる。
- 振戦: 四肢などに震えが見られることがある。
- 発声の抑制: 鳴き声などを上げなくなる。
- 鎮痛: 痛みを感じにくくなる状態(TI中は痛覚刺激に対する反応が低下する)。
- 意識・覚醒の維持: 見かけ上の不動状態とは裏腹に、周囲の状況に対する意識は保たれていることが多い(動物研究では、TI中に周囲の情報を処理し、逃走の機会をうかがっていることが示唆されている)。
- 自律神経系の変化: 心拍数や呼吸数の減少、体温の変化などが報告されている(ただし種差が大きい)。(Abrams et al., 2009; Wilczyńska et al., 2021)
TIの進化的意義については、いくつかの仮説があります(Gallup, 1977; Marx et al., 2008)。一つは「死んだふり(playing dead)」です。動かない獲物に対して捕食者の攻撃意欲が減退し、捕食を諦める可能性を高めます。また、捕食者が獲物を一時的に離した隙に逃走する機会を生み出すかもしれません。さらに、TI中の筋肉の硬直が、捕食者による飲み込みを物理的に困難にする可能性も指摘されています(Honma et al., 2006)。加えて、TI中の鎮痛作用や血圧低下は、攻撃を受けた際の損傷を軽減する効果があるかもしれません。
動物実験では、TIは物理的な拘束(restraint)と強い恐怖(intense fear)によって誘発されることが示されています(Gallup, Nash, Donegan, & McClure, 1971)。単に恐怖を感じるだけ、あるいは単に拘束されるだけでは、典型的にはTIは起こりにくいとされています。
1.2. TIと凍りつき(Freezing)の違い
TIは、しばしば防御カスケードの初期段階で見られる「凍りつき(Freezing)」と混同されますが、両者は異なる反応です。凍りつきは脅威を最初に察知した段階で起こり、体を動かさずに状況を評価し、次の行動(逃走や闘争)に備えるための、比較的主体的な要素を含む反応です。凍りつき中は覚醒レベルが高く、刺激への反応性も保たれています。一方、TIは逃走も闘争も不可能になった最終段階で起こる、より受動的で反射的な不動状態であり、外部刺激への反応性が著しく低下する点で大きく異なります(Marx et al., 2008; Hagenaars, 2016)。
2. 人間における緊張性不動(TI):トラウマ体験との関連
動物に見られるTIが、人間にも存在するのか? 長年、この問いは議論されてきましたが、近年、特に深刻なトラウマ体験との関連で、人間におけるTI様反応の存在が強く示唆されています。
2.1. 性的暴行とTI
人間におけるTIが最も注目されている文脈が、性的暴行(レイプ)です。SuarezとGallup (1979)は、性的暴行の状況が、動物における捕食者と被食者の関係、すなわち強い恐怖と物理的(あるいは心理的な)拘束・逃走不能という、TI誘発の条件を満たしていると指摘しました。
実際に、性的暴行のサバイバーからは、暴行中に体が麻痺したように動かせなかった、声が出せなかった、抵抗できなかったという報告が数多く寄せられています。BurgessとHolmstrom (1976)の研究では、レイプサバイバーの37%が、暴行中に何らかの形の麻痺(paralysis)を経験したと報告しています。これは後に「レイプ誘発性麻痺(rape-induced paralysis)」とも呼ばれました。
Gallianoら (1993)は、レイプサバイバー35名を対象とした研究で、動物のTIに見られる特徴(運動抑制、振戦、閉眼、呼吸数の増加、体温低下感など)が、暴行中に「不動(immobile)」であったと報告した群(全体の37%)において、「抵抗した(mobile)」群よりも有意に多く見られることを示しました。この研究は、レイプ中に起こる不動状態が、動物のTIに相当する人間の反応である可能性を示唆した点で画期的でした。
Heidtら (2005)は、小児期性的虐待(CSA)の経験を持つ臨床サンプルおよび非臨床サンプルにおいて、Tonic Immobility Scale-Child Abuse Form (TIS-C)を用いてTIの有病率と心理的影響を調査しました。その結果、52%以上の参加者がCSA中にTIを経験したと報告しました。特に、レイプやレイプ未遂を伴う虐待では、他の形態のCSAよりもTIが報告される割合が高く、恐怖の程度、持続的な傷害のリスク、逃れられないという認識、身体的拘束の程度が強い状況でTIが起こりやすいことが示唆されました。
Bovinら (2008)は、性的暴行サバイバーにおいて、暴行中の恐怖感と逃走不能感が強いほど、TIの程度が強くなること、そしてTIが恐怖・逃走不能感とPTSD症状重症度との関係を媒介することを発見しました。これは、TI体験そのものがPTSD発症の重要な要因となりうることを示唆しています。
2.2. 人間におけるTIの特徴
性的暴行サバイバーの報告や関連研究から、人間におけるTIには以下のような特徴が見られます(Marx et al., 2008; Bovin et al., 2008; Heidt et al., 2005; Galliano et al., 1993; Abrams et al., 2009)。
- 身体的特徴:
- 体が麻痺したように動かせない(随意運動の著しい抑制)
- 声が出せない、叫べない
- 筋肉が硬直する、あるいは逆に力が抜ける
- 震え
- 体が冷たく感じる
- 痛みを感じにくくなる(鈍麻)
- 心理的・認知的特徴:
- 極度の恐怖感、パニック感、死の恐怖
- 自分が自分でないような感覚(離人感)、現実感がない感覚(現実感消失)
- 時間の感覚の変化(非常にゆっくり感じたり、逆に飛んだりする)
- 周囲の状況や加害者の行動は比較的鮮明に覚えていることが多い(記憶の断片化を伴う場合もある)
動物のTIと同様に、人間においてもTIは突然始まり、突然終わることがあります。終了後は、激しい抵抗や逃走行動が再開されることもあります。重要なのは、動物研究が示唆するように、TI中であっても意識は保たれており、周囲の状況を処理している可能性が高いという点です。これは、後のトラウマ記憶の処理に影響を与える可能性があります。
2.3. TIは性的暴行に限られるのか?
TIが注目されるのは主に性的暴行の文脈ですが、強い恐怖と逃走不能が伴う他のトラウマ状況でも起こりうると考えられています。例えば、自然災害、交通事故、戦闘、動物による襲撃、さらにはジェットコースターのような極端なスリル体験などでも、TI様の反応が報告されています(Marx et al., 2008; Johnson, 1984)。飛行機事故の生存者の中に、負傷していないにも関わらず、座席から動けなくなっている乗客がいたという報告もあります(Johnson, 1984)。これらの事例は、TIが特定のトラウマタイプに限定されず、極度の脅威に対する普遍的なヒトの反応である可能性を示唆しています。
3. 緊張性不動(TI)とPTSDの関連メカニズム
なぜTIを経験することが、PTSDの発症リスクを高め、症状を重篤化させるのでしょうか? いくつかのメカニズムが考えられています。
3.1. 積極的防御の阻害と罪悪感・自己非難
TIは、逃走や闘争といった、より積極的な防御行動を不可能にします。トラウマ体験後、サバイバーは「なぜもっと抵抗しなかったのか」「なぜ逃げなかったのか」と、動けなかった自分を責めることがあります(Suarez and Gallup, 1979; Marx et al., 2008)。特に、社会的に「抵抗することが当然」とされるような状況(例えば性的暴行)では、この自己非難はさらに強まります。警察や司法関係者、医療従事者、さらには家族や友人といった周囲の人々から、「なぜ抵抗しなかったのか」という無理解な問いかけを受けることも、サバイバーの罪悪感や羞恥心を増幅させます(Abarbanel, 1986)。TIが自分の意志とは関係なく起こる不随意な生理反応であるという理解がなければ、サバイバーは「自分が抵抗しなかったから(あるいは抵抗をやめたから)被害が起きた・続いた」と誤って結論づけ、深い自己否定感に苛まれることになります。この罪悪感や自己非難は、PTSDの維持・悪化に繋がる重要な要因です。
3.2. 無力感とコントロール感の喪失
TIの体験は、極度の無力感(helplessness)と自己コントロール感の喪失を伴います。自分の身体を意のままに動かせないという体験は、自己効力感を著しく損ない、「自分は何もできなかった」という感覚を強く刻みつけます。このトラウマ中に経験された無力感が、トラウマ後も持続し、世界や他者、そして自分自身に対する信頼感を揺るがし、抑うつや不安、そしてPTSD症状(特に陰性感情や認知の変化)を引き起こす可能性があります(Foa, Zinbarg, & Rothbaum, 1992)。
3.3. 恐怖条件付けと記憶処理への影響
TIは、極度の恐怖下で起こる反応です。この強烈な恐怖体験は、TIに関連する状況や感覚を手がかり(トリガー)として、容易に恐怖反応が再燃するような強い恐怖条件付け(fear conditioning)を生み出す可能性があります。
また、TI中の意識は保たれている一方で、能動的な行動が抑制されている状態は、トラウマ記憶の処理に影響を与える可能性があります。行動が伴わないまま強烈な感覚情報や感情だけが刻まれ、それが断片化された形で記憶され、後にフラッシュバック(侵入的記憶)として生々しく再体験される一因となるかもしれません。TI中の離人感や現実感消失といった解離症状も、体験の統合を妨げ、記憶の断片化を促進する可能性があります(Marx et al., 2008; Lanius et al., 2002)。
3.4. 神経生物学的な変化
TIに関連する神経生物学的なメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、扁桃体を中心とする恐怖回路の過活動、視床下部-下垂体-副腎系(HPA系)の調節不全、セロトニン系やノルアドレナリン系といった神経伝達物質の関与などが動物研究で示唆されています(Gallup, 1977; Marx et al., 2008)。ヒトにおいても、TIを経験するような極度のストレスは、これらの神経生物学的なシステムに持続的な変化を引き起こし、PTSDの脆弱性を高める可能性があります。特に、TIが恐怖反応の極端な形態であると考えると、扁桃体の過活動や前頭前野による制御の低下といった、PTSDに特徴的な神経回路の変化と関連している可能性は高いでしょう(Shin, Rauch, & Pitman, 2005)。
また、TI中の不動状態と低覚醒状態(動物実験では脳波の徐波化が見られることがある)は、迷走神経系の機能、特に多重迷走神経理論で提唱されている「背側迷走神経複合体(Dorsal Vagal Complex: DVC)」のシャットダウン反応と関連している可能性も指摘されています(Porges, 2007, 2009)。このシャットダウン反応がトラウマ状況下で過剰に活性化されることが、PTSDの症状(解離、感情麻痺など)に関与しているという考え方です。
3.5. 研究による裏付け
これまでに、複数の研究がTIとPTSD症状との関連を裏付けています。
Heidtら (2005)の研究では、CSA中のTIが、うつ、不安、PTSD症状、そして外傷体験中の解離と正の相関があることを見出しました。
Fuséら (2007)は、成人性的暴行サバイバーにおいて、Tonic Immobility Scale (TIS)のスコアがPTSD症状(PCL-Cで測定)と有意に相関することを示しました。
Bovinら (2008)は、性的暴行サバイバーにおいて、TIが恐怖・逃走不能感とPTSD症状との関係を媒介することを統計的に示しました。
Abramsら (2009)は、大学生サンプルにおいて、様々なトラウマ(対人トラウマ、事故関連トラウマなど)におけるTI体験を調査し、TIQ(Tonic Immobility Questionnaire)を用いて測定されたTIが、PTSD症状(PCL-C)および外傷体験中の解離(PDEQ)と有意な正の相関を示すこと、特に外傷体験中の解離がTIの最も強い予測因子であることを見出しました。
de Kleineら (2018)は、慢性PTSD患者の大規模サンプルにおいて、心的外傷体験時(Peritraumatic)のTIと、フラッシュバックなどトラウマの再体験中(Re-experiencing)のTIの両方が高い頻度で見られることを報告しました。そして、再体験中のTIが、心的外傷体験時のTIと現在のPTSD症状重症度との関係を完全に媒介することを発見しました。これは、トラウマ後にTI様反応が再発することが、PTSD症状の維持に強く関わっている可能性を示唆しています。
Möllerら (2017)の前向き研究では、性的暴行直後のTIが、その後のPTSDおよび重度のうつ病の発症を有意に予測することを示しました。
これらの研究結果は、トラウマ中のTI体験が、単なる一時的な反応ではなく、その後の精神的健康、特にPTSDの発症と維持に深刻な影響を与える可能性を強く示唆しています。
4. 人間におけるTIの測定
人間におけるTIを客観的に測定することは困難であり、現在の研究は主に、トラウマ体験後の自己記入式質問紙を用いた回顧的報告に依存しています。以下に代表的な尺度をいくつか紹介します。
- Tonic Immobility Scale (TIS): Forsythらによって開発され、当初は小児期性的虐待用(TIS-C; Heidt et al., 2005で使用)と成人用(TIS-A; Fusé et al., 2007で使用)がありました。身体的不動、恐怖、解離などの側面を評価します。
- Tonic Immobility Questionnaire (TIQ): Taylorらによって開発され、Abrams et al. (2009)で使用されました。特定のトラウマに限定せず、より広範なトラウマ状況におけるTIを評価するために設計されています。身体的不動、恐怖、解離の3因子構造が示唆されています。
- TIS-TI (Trauma-Induced Tonic Immobility Scale): Hagenaars (2016) がTIS-Aを改変し、性的暴行以外のトラウマにも適用できるようにしたもの。
- PSS-SR (Posttraumatic Stress Symptom Scale – Self Report) のTI項目: de Kleineら (2018)の研究では、既存のPTSD症状尺度にTIに関する項目を追加する形で、心的外傷体験時と再体験時のTIを評価しています。
これらの尺度は、TIの有病率や他の心理的変数との関連を調査する上で有用ですが、回顧報告に伴う記憶バイアスや、TIと他の反応(凍りつきや解離)との区別が主観報告では難しいといった限界も抱えています。
5. 臨床的意義と介入への示唆
TIとPTSDの関連についての理解は、トラウマサバイバーへの臨床的支援において重要な意味を持ちます。
5.1. 心理教育と正常化(Normalizing)
サバイバーがトラウマ中に経験した「動けなかった」「声が出せなかった」という体験は、しばしば強い自己非難や羞恥心に繋がります。治療者は、TIが意志の弱さや同意ではなく、生命の危機に対する不随意で生得的な生存反応であることをサバイバーに伝える(心理教育)必要があります。この「正常化」は、サバイバーが抱える罪悪感や自己非難を軽減し、自己肯定感を回復する上で極めて重要です(Marx et al., 2008; Bovin et al., 2014)。TIは選択した行動ではなく、脳と身体が自動的に選択した反応なのです。
5.2. アセスメント
臨床家は、トラウマのアセスメントにおいて、TIの経験について具体的に尋ねることが重要です。「体が動かせなくなりましたか?」「声が出せなくなりましたか?」「体が麻痺したように感じましたか?」といった質問を通じて、TIの有無やその際の主観的な体験(恐怖、離人感、身体感覚など)を評価します。TIの経験は、PTSDのリスクや重症度、そして治療アプローチの選択に関わる重要な情報となります。
5.3. 治療的アプローチ
標準的なPTSD治療、特に暴露療法(Exposure Therapy)は、トラウマ記憶に伴う恐怖や苦痛を処理することを目的とします。しかし、TIを経験したサバイバーの場合、治療への反応が異なる可能性も指摘されています。
- 暴露療法への影響: 動物研究では、TIが自律神経系の覚醒レベル低下と関連することが示唆されています(Gentle, Jones, & Wooley, 1989)。もし人間においても同様に、TI経験者がトラウマ関連の刺激に対して覚醒レベルの低い反応(blunted arousal)を示す場合、恐怖記憶の活性化と処理を目的とする暴露療法の効果が十分に得られない可能性があります(Marx et al., 2008)。ただし、TI中の主観的な恐怖感は非常に強いことが多いため、一概には言えません。むしろ、暴露療法中にTI様反応(フリーズやシャットダウン)が誘発される可能性も考慮する必要があります。
- 身体志向アプローチの重要性: TIは極めて身体的な体験です。そのため、身体感覚への気づきを促し、トラウマに関連して身体に凍りついたエネルギーや未完了の防御反応(逃走や闘争)を解放することを目指す身体志向の心理療法(Somatic Experiencing, Sensorimotor Psychotherapyなど)が有効である可能性があります(Levine, 1997; Ogden & Minton, 2002)。これらのアプローチは、サバイバーが身体感覚を通じてTI体験を処理し、自己調整能力を取り戻すのを助けることを目指します。
- 能動的対処の促進: TI体験に伴う無力感を克服するために、治療の中でサバイバーが能動的に対処する感覚を取り戻せるような介入(アサーション・トレーニング、自己防衛スキルの学習など)が有効な場合もあります。
TIを経験したサバイバーへの治療においては、画一的なアプローチではなく、個々の体験と反応特性に合わせた、柔軟で統合的なアプローチが求められます。
6. 課題と今後の研究
人間におけるTIの研究はまだ発展途上であり、多くの課題が残されています。
- 測定法の限界: 回顧的な自己報告への依存は大きな限界です。TI中の客観的な生理学的指標(心拍変動、皮膚コンダクタンス、筋電図など)を測定する前向き研究や実験研究が求められます。
- TIと他の反応との区別: TI、凍りつき(Freezing)、周縁性解離(Peritraumatic Dissociation)は、現象として重なる部分があり、特に自己報告では区別が困難な場合があります。これらの反応の異同を神経生物学的レベルも含めて明らかにする必要があります。Abramsら(2009)はTIQの因子分析からTIの要素として解離を見出しており、TIと解離が連続的なものである可能性も探求されるべきです。
- 神経生物学的メカニズムの解明: ヒトにおけるTI中の脳活動や自律神経系のダイナミクス、内分泌系の反応など、神経生物学的な基盤の解明が急務です。動物モデルとの比較研究も重要となります。
- 多様なトラウマにおけるTI: 性的暴行以外のトラウマ(事故、災害、戦闘など)におけるTIの有病率や特徴、予後への影響についても、さらなる研究が必要です。
- 発達的視点: TIの感受性が年齢や発達段階によってどのように変化するのか、特に小児期や思春期のトラウマにおけるTIの影響についての研究が不足しています。
- 長期的影響: TI体験が、PTSD以外の精神疾患(うつ病、不安障害、解離性障害など)や身体的健康問題にどのように影響するのか、長期的な追跡研究が必要です。
結論:TIへの理解を深め、回復を支援するために
緊張性不動(TI)は、もはや動物だけの特殊な反応ではありません。それは、人間が極度の恐怖と逃れられない脅威に直面したときに起こりうる、深く根差した不随意な生存反応です。特に性的暴行などのトラウマ状況下でTIを経験することは稀ではなく、その体験は後のPTSDの発症や悪化、そして深刻な自己非難や罪悪感と密接に関連しています。
TIを「抵抗しなかったこと」の証拠や意志の弱さと見なすことは、根本的な誤解です。サバイバー自身も、支援者も、そして社会全体も、TIがコントロール不可能な生理的反応であることを理解し、受け入れることが、回復への第一歩となります。
臨床家は、トラウマサバイバーのアセスメントと治療において、TIの経験に注意を払い、心理教育を通じてその意味を正常化し、個々の反応に合わせた治療的アプローチを提供する必要があります。
今後の研究によって、人間におけるTIのメカニズムとその影響がさらに解明されることが期待されます。TIへの科学的理解を深めることは、トラウマサバイバーへの偏見を減らし、より効果的な支援を提供するための基盤となるでしょう。「凍りつく」という体験が決して個人の責任ではないことを社会が認識し、サバイバーが安心して回復への道を歩めるよう支援していくことが、私たちに求められています。
引用文献
- Abarbanel, G. (1986). Rape and resistance. Journal of Interpersonal Violence, 1, 100–105.
- Abrams, M. P., Carleton, R. N., Taylor, S., & Asmundson, G. J. G. (2009). Human tonic immobility: Measurement and correlates. Depression and Anxiety, 26(6), 550–556.
- Altman, J., Brunner, R. L., & Bayer, S. A. (1973). The hippocampus and behavioral maturation. Behavioral Biology, 8(5), 557–596.
- Amit, Z., & Galina, Z. H. (1986). Stress-induced analgesia: adaptive pain suppression. Physiological Reviews, 66(4), 1091–1120.
- Baranyiova`, E. (1990). Effects of serotonin on the food intake in chicks in the post-hatching period. Acta Veterinaria Brno, 59(1-2), 23-33.
- Bovin, M. J., Jager-Hyman, S., Gold, S. D., Marx, B. P., & Sloan, D. M. (2008). Tonic immobility mediates the influence of peritraumatic fear and perceived inescapability on posttraumatic stress symptom severity among sexual assault survivors. Journal of Traumatic Stress, 21(4), 402–409.
- Bovin, M. J., Dodson, T. S., Smith, B. N., Gregor, K., Marx, B. P., & Pineles, S. L. (2014). Does guilt mediate the association between tonic immobility and posttraumatic stress disorder symptoms in female trauma survivors? Journal of Traumatic Stress, 27(6), 721–724.
- Braud, W. G., & Ginsburg, H. J. (1973). Immobility reactions in domestic fowl (Gallus gallus) less than 7 days old: resolution of a paradox. Animal Behaviour, 21(1), 104–108.
- Burgess, A. W., & Holmstrom, L. L. (1976). Coping behavior of the rape victim. American Journal of Psychiatry, 133(4), 413–418.
- Bures, J., & Buresova, O. (1956). The influence of reflex acoustic epilepsy and reflex inhibition (“animal hypnosis”) by spreading EEG depression. Physiologia Bohemoslovenica, 5(4), 395-400.
- Burghardt, G. M. (1991). Cognitive ethology and critical anthropomorphism: A snake with two heads and hognose snakes that play dead. In C. A. Ristau (Ed.), Cognitive ethology: The minds of other animals (pp. 53–90). Lawrence Erlbaum Associates.
- Carli, G. (1969). Dissociation of electrocortical activity and somatic reflexes during rabbit hypnosis. Archives Italiennes de Biologie, 107(2), 219–234.
- Carli, G. (1974). Blood pressure and heart rate in the rabbit during animal hypnosis. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 37(3), 231–237.
- Carli, G., Farabollini, F., Fontani, G., & Grazzi, F. (1984). Physiological characteristics of pressure immobility: effects of morphine, naloxone and pain. Behavioural Brain Research, 12(1), 55–63.
- Collias, N. E. (1952). The development of social behavior in birds. The Auk, 69(2), 127–159.
- de Kleine, R. A., Hagenaars, M. A., & van Minnen, A. (2018). Tonic immobility during re-experiencing the traumatic event in posttraumatic stress disorder. Psychiatry Research, 270, 1105–1109.
- Desforges, M. F., & Wood-Gush, D. G. (1975). Behavioural differences between Aylesbury and wild mallard ducks. Habituation and flight reactions. Animal Behaviour, 23(3), 692-697.
- Fanselow, M. S., & Lester, L. S. (1988). A functional behavioristic approach to aversively motivated behavior: Predatory imminence as a determinant of the topography of defensive behavior. In R. C. Bolles & M. D. Beecher (Eds.), Evolution and learning (pp. 185–211). Lawrence Erlbaum Associates.
- Fiszman, A., Mendlowicz, M. V., Marques-Portella, C., Volchan, E., Coutinho, E. S., Souza, W. F., … & Figueira, I. (2008). Peritraumatic tonic immobility predicts a poor response to pharmacological treatment in victims of urban violence with PTSD. Journal of Affective Disorders, 107(1-3), 193–197.
- Flores, G., Silva-Gómez, A. B., Barbeau, D., Srivastava, L. K., Zamudio, S. R., & De La Cruz, F. (2005). Effect of excitotoxic lesions of the neonatal ventral hippocampus on the immobility response in rats. Life sciences, 76(20), 2339-2348.
- Foa, E. B., Zinbarg, R., & Rothbaum, B. O. (1992). Uncontrollability and unpredictability in post-traumatic stress disorder: an animal model. Psychological Bulletin, 112(2), 218–238.
- Forsyth, J. P., Marx, B., Heidt, J., Fuse´, T. M. K., & Gallup, G. G., Jr. (2000). The Tonic Immobility Scale—Child Form. Albany, NY: Authors.
- Fusé, T., Forsyth, J. P., Marx, B. P., Gallup, G. G., & Weaver, S. (2007). Factor structure of the Tonic Immobility Scale in female survivors of sexual assault: An exploratory and confirmatory factor analysis. Journal of Anxiety Disorders, 21(3), 265–283.
- Gagliardi, G. J., Gallup, G. G., Jr., & Boren, J. L. (1976). Effect of different pupil size ratios on tonic immobility in chickens. Bulletin of the Psychonomic Society, 8(1), 58-60.
- Galliano, G., Noble, L. M., Travis, L. A., & Puechl, C. (1993). Victim reactions during rape/sexual assault: A preliminary study of the immobility response and its correlates. Journal of Interpersonal Violence, 8(1), 109–114.
- Gallup, G. G., Jr. (1974). Animal hypnosis: factual status of a fictional concept. Psychological Bulletin, 81(11), 836–853.
- Gallup, G. G., Jr. (1977). Tonic immobility: The role of fear and predation. The Psychological Record, 27(1), 41–61.
- Gallup, G. G., Jr., Nash, R. F., Donegan, N. H., & McClure, M. K. (1971). The immobility response: A predator-induced reaction in chickens. The Psychological Record, 21(4), 513–519.
- Gentle, M. J., Jones, R. B., & Woolley, S. C. (1989). Physiological changes during tonic immobility in Gallus gallus var domesticus. Physiology & Behavior, 46(5), 843–847.
- Gilman, T. T., Marcuse, F. L., & Moore, A. U. (1950). Animal hypnosis: a study in the induction of tonic immobility in chickens. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 43(2), 99–111.
- Hagenaars, M. A. (2016). Tonic immobility in a large community sample. Journal of Experimental Psychopathology, 7(2), 246-260.
- Heidt, J. M., Marx, B. P., & Forsyth, J. P. (2005). Tonic immobility and childhood sexual abuse: a preliminary report evaluating the sequela of rape-induced paralysis. Behaviour Research and Therapy, 43(9), 1157–1171.
- Hennig, C. W., Dunlap, W. P., & Gallup, G. G., Jr. (1976). The effects of defensive distance and opportunity to escape on tonic immobility in Anolis carolinensis. The Psychological Record, 26(3), 313–320.
- Hoagland, H. (1928). The mechanism of tonic immobility (“animal hypnosis”). The Journal of General Psychology, 1(3-4), 426-447.
- Hogan, J. A. (1965). An experimental study of conflict and fear: an analysis of behaviour of young chickens towards a mealworm. Part 1. The behaviour of chickens which do not eat the mealworm. Behaviour, 25(1-2), 45-97.
- Holmes, S. J. (1906). Death-feigning in Ranatra. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 16(3), 200-216.
- Honma, A., Oku, S., & Nishida, T. (2006). Adaptive significance of death-feigning posture as a specialized inducible defence against gape-limited predators. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 273(1594), 1631–1636.
- Humphreys, K. L., Sauder, C. L., Martin, E. K., & Marx, B. P. (2010). Tonic immobility in childhood sexual abuse survivors and its relationship to posttraumatic stress symptomatology. Journal of Interpersonal Violence, 25(2), 358–373.
- Johnson, D. (1984). Just in case: A passenger’s guide to airline safety and survival. Plenum Press.
- Jones, R. B. (1986). The tonic immobility reaction of the domestic fowl: a review. World’s Poultry Science Journal, 42(1), 82-97.
- Kalaf, J., Coutinho, E. S., Vilete, L. M., Luz, M. P., Berger, W., Mendlowicz, M., … & Figueira, I. (2017). Sexual trauma is more strongly associated with tonic immobility than other types of trauma–A population based study. Journal of Affective Disorders, 215, 71-76.
- Klemm, W. R. (1971). Neurophysiologic studies of the immobility reflex (‘animal hypnosis’). Neurosciences Research, 4, 165-212.
- Kozlowska, K., Walker, P., McLean, L., & Carrive, P. (2015). Fear and the defense cascade: clinical implications and management. Harvard Review of Psychiatry, 23(4), 263–287.
- Lanius, R. A., Williamson, P. C., Boksman, K., Densmore, M., Gupta, M., Neufeld, R. W., … & Menon, R. S. (2002). Brain activation during script-driven imagery induced dissociative responses in PTSD: a functional magnetic resonance imaging investigation. Biological Psychiatry, 52(4), 305–311.
- Levine, P. A. (1997). Waking the tiger: Healing trauma. North Atlantic Books.
- Lupfer-Johnson, G., & Murphy, E. S. (2003). Tonic immobility (“death feigning”) in the lizard Anolis carolinensis: effect of stimulus distance. The Psychological Record, 53(3), 439-451.
- Marks, I. M. (1987). Fears, phobias, and rituals: Panic, anxiety, and their disorders. Oxford University Press.
- Marx, B. P., Forsyth, J. P., Gallup, G. G., Jr., Fusé, T., & Lexington, J. M. (2008). Tonic immobility as an evolved predator defense: Implications for sexual assault survivors. Clinical Psychology: Science and Practice, 15(1), 74–90.
- Maser, J. D., & Gallup, G. G., Jr. (1974). Tonic immobility in the chicken: Catalepsy potentiation by uncontrollable shock and alleviation by imipramine. Psychosomatic Medicine, 36(3), 199-205.
- Maser, J. D., & Gallup, G. G., Jr. (1977). Tonic immobility and related phenomena: a partially annotated, tricentennial bibliography, 1636-1976. The Psychological Record, 27(2), 177-217.
- Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault–a common reaction predicting post‐traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(8), 932–938.
- Nauta, W. J., & Karten, H. J. (1970). A general profile of the vertebrate brain, with sidelights on the ancestry of cerebral cortex. In F. O. Schmitt (Ed.), The Neurosciences: Second study program (pp. 7-26). Rockefeller University Press.
- Nash, R. F., & Gallup, G. G., Jr. (1975). Aversiveness of the induction of tonic immobility in the chickens (Gallus gallus). Journal of Comparative and Physiological Psychology, 88(3), 935–939.
- Nash, R. F., & Gallup, G. G., Jr. (1976). Habituation and tonic immobility in domestic chickens. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 90(9), 870–876.
- O’Brien, T. J., & Dunlap, W. O. (1975). Tonic immobility in the blue crab (Callinectes sapidus, Rathbun): Its relation to threat of predation. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 89(1), 86–94.
- Ogden, P., & Minton, K. (2002). Sensorimotor approach to processing traumatic memory. In C. R. Figley (Ed.), Brief treatments for the traumatized: The state of the art (pp. 125–147). Greenwood Press.
- Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., & Weiss, D. S. (2003). Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 129(1), 52–73.
- Pavlov, I. P. (1923). Die Identität der Hemmung mit dem Schlaf und der Hypnose. Skandinavisches Archiv Für Physiologie, 44(1), 42-58.
- Porges, S. W. (2007). The polyvagal perspective. Biological Psychology, 74(2), 116–143.
- Porges, S. W. (2009). The polyvagal theory: New insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 76(Suppl 2), S86–S90.
- Preyer, W. (1881). Die Entdeckung des Hypnotismus. Gebrüder Paetel.
- Ratner, S. C. (1967). Comparative aspects of hypnosis. In J. E. Gordon (Ed.), Handbook of clinical and experimental hypnosis (pp. 550–587). Macmillan.
- Ratner, S. C., & Thompson, R. W. (1960). Immobility reactions (fear) of domestic fowl as a function of age and prior experience. Animal Behaviour, 8(3-4), 186–191.
- Russell, D. E. H. (1974). The politics of rape: The victim’s perspective. Stein and Day.
- Schauer, M., & Elbert, T. (2010). Dissociation following traumatic stress. Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology, 218(2), 109–127.
- Shin, L. M., Rauch, S. L., & Pitman, R. K. (2005). Functional neuroimaging studies in PTSD: A critical review. In J. J. Vasterling & C. R. Brewin (Eds.), Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives (pp. 59-82). Guilford Press.
- Suarez, S. D., & Gallup, G. G., Jr. (1979). Tonic immobility as a response to rape: A theoretical note. The Psychological Record, 29(3), 315–320.
- Taylor, S., Stapleton, J., & Asmundson, G. J. G. (2007). Tonic Immobility Questionnaire-Revised. Unpublished scale.
- Ullman, S. E., & Knight, R. A. (1995). Women’s resistance strategies to different rapist types. Criminal Justice and Behavior, 22(3), 263–283.
- Volchan, E., Rocha-Rego, V., Bastos, A. F., Oliveira, J. M., Franklin, C., Gleiser, S., … & Figueira, I. (2017). Immobility reactions under threat: A contribution to human defensive cascade and PTSD. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 76, 29–38.
- Wilczyńska, A., Ziętek, J., Teodorowski, O., Winiarczyk, S., & Adaszek, Ł. (2021). Effect of tonic immobility induction on selected physiological parameters in Oryctolagus cuniculus f. Domesticus rabbits. Medycyna Weterynaryjna, 77(6), 295-299.