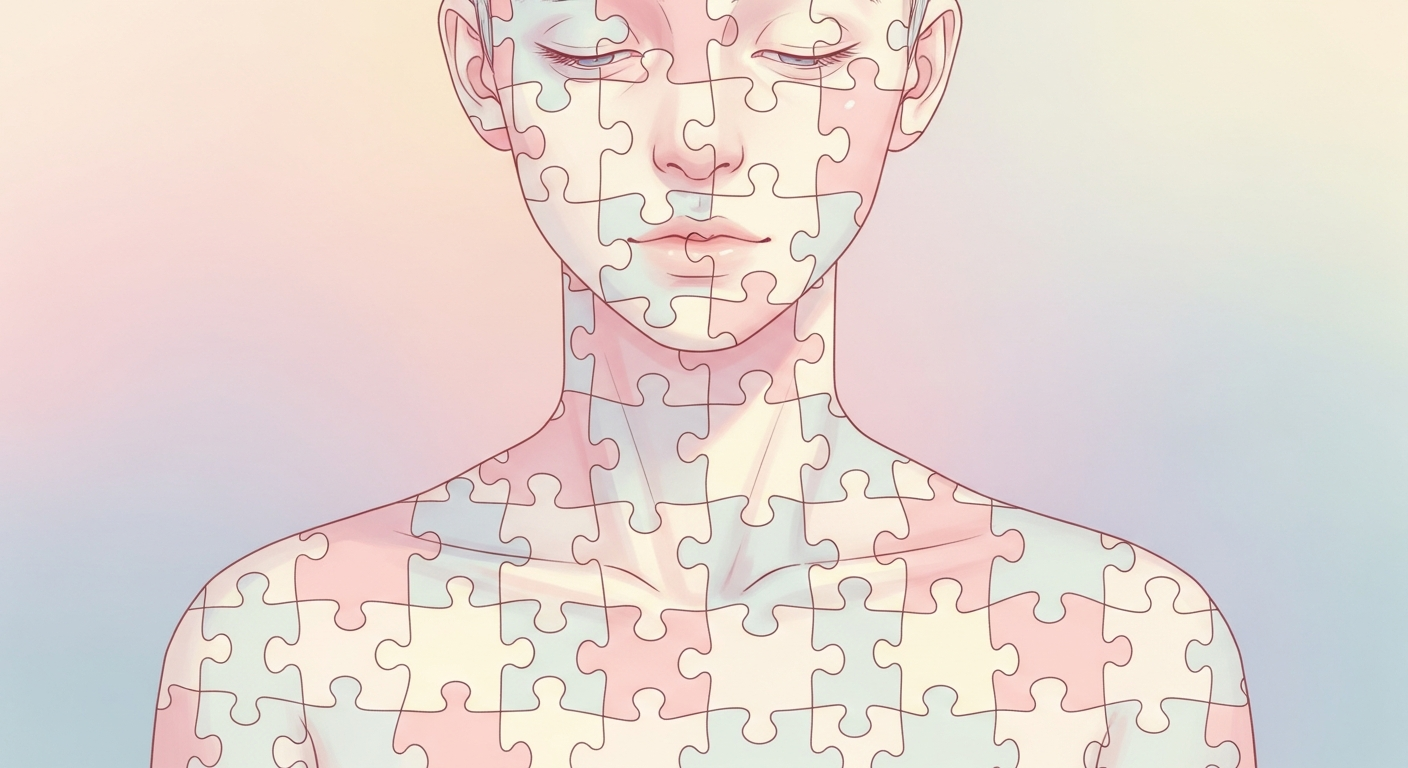複雑な内面世界を理解するための「言葉」
『人格が複数ある』ときくと、すぐに解離性同一性障害が浮かんでしまいますが、実際に『人格が複数ある』という状態は、一様ではありません。ここでは、DSM-5-TR, ICD-11を基準に、Redditで考察されている『人格が複数ある』という状態について解説します。
第1章:解離性障害のスペクトラム – 主要なサブタイプ
ここでは、『人格が複数ある』状態の代表格である解離性同一性障害(DID)、他の特定される解離性障害(OSDD)を中心に、周辺的な状態像について解説します。
1-1. 解離性同一性障害(DID)の診断基準(DSM-5-TR)
DIDと診断されるためには、以下の5つの基準(A~E)をすべて満たす必要があります。
- A. 複数の人格(アイデンティティの分裂)
- 自分の中に、2つ以上のハッキリと区別できる人格(または「自己の状態」)が存在し、それらが入れ替わることで、本来の自分という感覚が途切れてしまいます。
- この人格の交代に伴い、感情、行動、記憶、考え方などが大きく変化します。この変化は、他人から見てわかることもあれば、自分自身で感じることもあります。
- B. 記憶の喪失(健忘)
- 日常的な出来事や自分の大切な個人情報、つらい体験などを、ただの物忘れでは説明できないほど思い出せなくなります。
- 人生の一部が空白になる
- 結婚や出産といった重要なライフイベントや、学生時代の思い出など、自分自身の歴史の一部がすっぽりと抜け落ちてしまうことがあります。
- できていたはずのことが分からなくなる
- 毎日していた仕事のやり方、パソコンの使い方、料理や運転の仕方など、身についていたはずのスキルや知識を突然思い出せなくなることがあります。
- 身に覚えのないものが見つかる
- 買った記憶のない服がクローゼットにあったり、自分で書いたはずの文章や絵を見ても全く覚えがなかったりします。
- 気づいたら知らない場所にいる(解離性とん走)
- 記憶がないまま移動してしまい、突然、知らない街や職場、あるいは自宅のクローゼットの中などで「我に返る」ことがあります。
- 日常的に時間が飛ぶ感覚がある
- 「ブラックアウト」や「時間の喪失」と呼ばれる体験をし、「何かをしている途中で、はっと気づく」といったことが起こります
- 人生の一部が空白になる
- 日常的な出来事や自分の大切な個人情報、つらい体験などを、ただの物忘れでは説明できないほど思い出せなくなります。
- C. 生活への支障
- これらの症状が原因で、精神的に大きな苦痛を感じたり、仕事や人間関係など、日常生活に深刻な問題が生じたりしています。
- D. 文化・宗教的なものではない
- これらの体験は、その地域の文化や宗教における正常な儀式(例:憑依)などではありません。
- (注:子どもの場合、これらは「空想の友達」との遊びなどとは明確に区別されます。)
- E. 薬物や他の病気が原因ではない
- これらの症状は、薬物やお酒の影響、またはてんかん発作のような他の病気が原因で起きているわけではありません。
- 主な特徴:2つ以上の明確に分離した人格状態(アルター)と、日常的な出来事やトラウマ体験に関する反復的な記憶喪失(健忘)の両方が存在する。
- 原因の例:ほとんどの場合、幼少期の深刻で反復的なトラウマが原因とされる。
- 議論のポイント:解離性障害のスペクトラムにおいて最も重い状態と見なされることが多い。治療は長期にわたることが多く、アルター間の協調関係を築くことが目標となる。
1-2. 他の特定される解離性障害(OSDD)の診断基準(DSM-5-TR)
OSDDは、解離症状が原因で日常生活に深刻な問題や苦痛が生じているものの、DIDなどの特定の解離性障害の診断基準を完全には満たさない場合に用いられます。
以下は、OSDDに分類される代表的な4つの状態です。
OSDD-1:DIDに類似するが、基準を完全には満たさない
OSDDの中で最もDIDに近く、複数の人格状態(システム)の形成に関連すると考えられています。幼少期のトラウマが原因である点もDIDと共通しています。Redditでは、「1a」と「1b」に分けて理解することが一般的です。
- OSDD-1a(コミュニティ用語)
- 主な特徴:アルターが明確に分離しておらず「バージョン違いの自分」のように感じられるが、記憶喪失(健忘)は存在する。
- DIDとの違い:アルターの区別が明確でない(DIDの基準Aを満たさない)。
- 議論のポイント:当事者からは「別人格というより、気分の波や年齢が退行した自分という感覚」と語られることが多い。
- OSDD-1b(コミュニティ用語)
- 主な特徴:明確に分離したアルターが存在するが、彼らの間に顕著な記憶喪失(健忘)がない、あるいは非常に少ない。
- DIDとの違い:記憶喪失が顕著でない(DIDの基準Bを満たさない)。
- 議論のポイント:DIDに非常に近く、治療の過程や新たなストレスによってDIDに診断が移行する可能性も指摘される。アルター間の記憶は共有されているが、感情的な繋がりが薄い「感情的健忘」や、記憶がぼんやりする「グレイアウト」を経験することがある。
OSDD-2, 3, 4:トラウマ以外の要因も含む解離症状
これらはOSDD-1とは異なり、必ずしも幼少期トラウマやシステム形成とは関連しない解離状態を指します。
- OSDD-2
- 主な特徴:長期的で強烈な強制的説得(カルトによる洗脳、拷問など)の結果として生じる、アイデンティティの混乱。
- DIDとの違い:アルターの形成は見られず、成人期に発症することもある。
- 議論のポイント:複雑性PTSD(C-PTSD)との併存が多いとされる。
- OSDD-3
- 主な特徴:深刻なストレスイベントへの急性反応として現れる解離症状。知覚の変化や麻痺など、身体的な症状を伴うことがある。
- DIDとの違い:症状は短期(通常1ヶ月未満)で一過性であり、アルターは形成されない。
- 議論のポイント:急性ストレス障害(ASD)との関連で議論されることが多い。
- OSDD-4
- 主な特徴:意図せず、望まない形でトランス状態に陥る。周囲への反応が著しく低下する。
- DIDとの違い:宗教的・文化的な儀式の一部として起こるものは除外される。アルターの存在とは区別される孤立した症状。
- 議論のポイント:他の精神疾患の症状として現れることもあるため、慎重な鑑別が必要とされる。
1-3. 離人症・現実感喪失障害 (DPDR)
- 主な特徴:自分が自分ではないような感覚(離人感)や、周囲の世界が現実ではないように感じる感覚(現実感喪失)が、持続的または反復的に生じる。
- 原因の例:トラウマ、深刻なストレス、薬物の影響など様々。
- DIDとの違い:アイデンティティの断絶(アルターの存在)や記憶喪失は主症状ではない。
- 議論のポイント:DIDやOSDDの症状の一部として離人感・現実感喪失が起こることも多いが、これらが主症状の場合は独立した診断となる。
1-4. 解離性健忘
- 主な特徴:重要な個人的情報を思い出せなくなる記憶喪失が主症状。
- 原因の例:通常、トラウマティックな出来事や極度のストレスが原因。
- DIDとの違い:記憶喪失は生じるが、アルターは存在しない。
- 議論のポイント:特定の期間の記憶をすべて失う「限局性健忘」が一般的。まれに、自分の素性を忘れて突然旅に出る「解離性とん走」というサブタイプを伴うことがある。
1-5. 部分的解離性同一性障害 (PDID) ICD-11
- 主な特徴:ICD-11で採用された診断名。一つの支配的な人格(ホスト)がほとんどの時間、意識の表層にいるが、他の非支配的な人格状態が思考や感情、行動に不意に侵入し、内部から干渉する。
- 原因の例:DIDと同様、幼少期のトラウマが原因とされる。
- DIDとの違い:アルターによる完全な意識の乗っ取り(スイッチ)は稀で、健忘も限定的。
- 議論のポイント:DSM-5におけるOSDD-1bの概念に非常に近いとされ、OSDD-1の代替的な診断名として注目されている。
第2章:システムの全体像 – 構造で読み解く多様な内面世界
DID/OSDDにおける「システム」とは、一つの身体の中に存在するアルターたちの総体であり、彼らが織りなす内なる社会そのものを指します。その構造はシステムごとに千差万別で、非常に複雑なものもあります。
2-1. Covert(潜在型) vs Overt(顕在型):ほとんどのDIDは「見えない」
- Overt(オーヴァート、顕在型):誰が見ても「別人」に入れ替わったことが分かる劇的なタイプ。実際には非常に稀。
- Covert(カヴァート、潜在型):外部から症状が非常に分かりにくいタイプで、当事者の大多数がこれに属する。システムが社会に適応し、自らを守るための生存戦略であり、「見えないのが普通」という認識が当事者間では共有されている。
2-2. Polyfragmented System(多重断片化システム):100人を超える複雑な構造
単にアルターの数が多い(一般に100以上)だけでなく、構造が極めて複雑で階層的なシステム。
- Fragment(フラグメント):特定の感情や記憶のみを担う断片的なパートが多数存在する。
- Subsystem(サブシステム):システムの中に「システム内システム」とも言える入れ子構造が存在する。
このような極端な断片化は、多くの場合、幼少期から長期間にわたる深刻な虐待の結果として形成されると考えられています。
第3章:内なる社会の住人たち – アルター(人格)の役割(ロール)
システムは、それぞれが特定の「役割(ロール)」を担うアルターたちが協力し合うことで維持されています。ここでは、主要な役割を紹介します。
3-1. システム運営の要:主要な機能的役割
- Host(ホスト):日常生活の大部分を担う「システムの顔」。
- Protector(プロテクター):システムを内外の危険から守る役割。
- Gatekeeper(ゲートキーパー):アルターの交代や記憶へのアクセスを管理する「門番」。
- Persecutor(パーセキューター):自傷行為を促すなど、一見敵対的に見えるが、その本質は「内面化された加害者」であり、歪んだ形でシステムを守ろうとしている存在。
- Caretaker(ケアテイカー):内部の幼いアルターや傷ついたアルターの世話をする母親的な役割。
3-2. 時間と記憶を抱える者たち:発達段階に基づく役割
- Little(リトル):子ども(通常12歳以下)のアルター。トラウマの純粋な感情や記憶を保持していることが多い。
- Teen/Middle(ティーン/ミドル):思春期のアルター。
3-3. どこから来たのか?:起源に基づく役割
- Introject(イントロジェクト):外部の人物(加害者、親など)の特性を取り込んで形成されたアルターの総称。
- Fictive(フィクティブ):アニメやゲームなどフィクションの登場人物を元にしたアルター。
- Factive(ファクティブ):実在の人物(歴史上の人物など)を元にしたアルター。
まとめ
『人格が複数ある』という状態は、DID以外にもOSDD -1a、OSDD-1bなど様々な状態があります。OSDD-1aとOSDD-1bは診断基準にはなく、明確に両者を分離できないのですが、臨床的な区分としては役に立つと感じます。